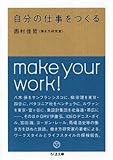自分の仕事をつくる
この本のテーマは結構シンプルで、内容も読み易く、働き方研究家というのをライフワークにされている著者の方が色々な会社/個人について「働き方」を取材したまとめになっていてこう書いてしまうと、何だか味気ないけど、一番の売りというのがこの本でとりあげている会社・個人っていうのが自分のツボにはまるものばかりで、特に
- サーフボードのシェイパーであり、もちろんサーファーでも植田義則さん
- デザイン関連では有名なIDEO。(そっち系の業界はそんなに精通しているわけじゃないけど、以前発想する会社! ― 世界最高のデザイン・ファームIDEOに学ぶイノベーションの技法を読んでIDEOの名前はしっていました)
っていう名前を目次読んでいる時に気づいてからものすごくワクワクして本を読みました。
それぞれの人や会社の人達がどういう気持で普段働いているかというのは本書を読んでいただくとして、自分の心にズシっと響いた言葉をいくつか引用します
その人がそこに「いる」感じのしない働き手や仕事が、世の中で増えてゆく。それは僕には耐え難いことです。320ページより
IT関連の仕事で、ある程度業務が標準化したり定型化出来るものはアウトソーシング化によって、外部に委託される事があるかと思いますが、経営的な数値だけみればたしかに効率的な所はあるのかもしれません。
ただその結果
- それは契約なので出来ませんと言われてしまうユーザ
- (そんな簡単なことすぐに対応できるのに・・・)と心で思いつつ契約上やってはいけないために手を出さないアウトソーシング先の会社のエンジニア
なんていうことがはるか数年前に自分も経験したことがあるし、日々のキャリアカウンセリングの場面でも似たような相談を受けることっていうのが過去何度かありましたが、その根底にあるのが、そこに「いる」感じ、つまり、働き手自身の存在意義っていうのが仕事場で得られないからくることなのかなぁと思います。
多少矛盾しそうなことを書きますが、今の仕事でそこに「いる」という感覚を得るのが世の中全てではないんじゃないかと最近少しづつ考えるようになってきました。
もちろん人によっては幸い、仕事でそこに「いる」感じのする人たちが多数いる恵まれている環境や、その人自身が「いる」という感覚を日常的に仕事を通じて味わえる人もいると思うのですが、全員がそういう感覚を得られるかというとやや疑問なところがあるし、仕事だけに求めるのは、長い人生を考えると何か無理があるように感じてます。
私たちは本当に会社に能力を売ることで対価を得ているのか?という疑問である。人は能力を売るというより「仕事を手に入れる」ために、会社へ通っている。そんな側面はないだろうか。
〜中略〜
ところで、私たちが会社から仕事を買っているとしたら、そこで支払っている対価はなんだろう。それは「時間」である。そして時間とは、私たちの「いのち」そのものである。(267-268ページより)
仕事でそこに「いる」という感覚を味わうことが無いとか、味わうチャンスが基本少ない状態でいるっていうのはここで引用した、自分の時間っていうのを会社に対して投資した結果得られるモノが少なすぎる状態かなと思い、それっていうのはあまり幸せな感じがしないのかなと思います。
だとすると、自分の時間っていうのを会社に対して投資する割合っていうのを今までよりは抑えたとしても、それ以外の所で、自分が「いる」という感覚を味わえる「場」への割合を増やすような頭の切り替えではないけど持っていても決して損ではないかなぁと個人的には思っています。
眠くなってきたのでなんだか自分でも考えがまとまっているんだかよくわからないけど、関連しそうなことを気が向いたらまた書きます。
筑摩書房
売り上げランキング: 2266

 「生きるための仕事」ではなく
「生きるための仕事」ではなく 仕事の迷路に迷ったら、
仕事の迷路に迷ったら、 「働く」ことと「生きる」ことに橋を架けてくれる本です
「働く」ことと「生きる」ことに橋を架けてくれる本です